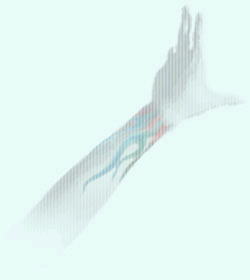
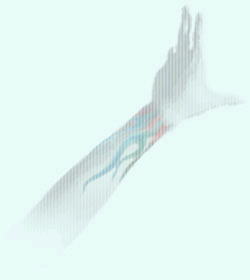
Bleed it out
フックに架けたシャワーから延々降り注ぐ温かい雨に、彼はただ打たれていた。
湯気に霞んだ後姿は、安堵と不安を半々に掻き立てる。
「おーい?」
安気な風に繕った声音の微かな揺らぎが、水音に紛れることを願いながら、呼んでみる。
呆れる程、様々なことに無頓着な癖に、彼は自分の顔色には敏い。
「あ、お帰り、なさい」
手の甲で顔を拭いながら振り向いた。
眼鏡無しの顔は久し振りだ。
それだけでない違和感が、不安の楔をさらに、ぐさりと突き立てる。
「髪、洗おっか?」
「お願いします」
泡が滑らかに指の間を落ちていく感触と、慣れた匂いが、いくらか気を鎮めてくれた。
髪と頭皮に一番優しいタイプのサロン用だが、
最初にシャンプーしてやったときは、薬くさいと散々抗議された。
(僕、普段も薬品だらけの中で仕事してるんですよ、
お風呂のとき位違う匂いでくつろぎたいのに)
「この瓶が空いたら、違うのになるぜ、シャンプー」
「え?」
「店で使うのが総入れ替え。
ココナツオイルベースでラベンダーの香りだとさ」
「アロマ効果狙いですか?」
「もちろんそれも、だけどな。いわゆる地球に優しい製品なんだと。
泡を流しても環境汚染しないとか、動物実験してないって
売り込まれて、社長もすっかり乗せられてんだわ。
まあイメージ商売だし」
「捲簾」
切迫した声は、欲望と違う色だ。
水のヴェール越しに、しゃにむに求める唇に、捲簾はありったけの柔らかさで応えた。
「どうしたよ」
「駄目ですか」
「ほんとにシてぇの?」
シャワーの栓を締める。もう、シャツも、カーゴパンツもずぶ濡れだ。
白い額に貼り付いた髪を払って、目を覗き込む。
慌しく瞬いた茶の眸からは、違う温度の雫がこぼれた。
涙は−生理的なもの以外−初めてだった。
流されてやりたい衝動を、ぐっと堪える。
「不安なこととか、誤魔化したいこと、セックスでなしくずしにすんのは、
何の解決にもならないだろ?
ただ、見えないとこに押し込んでくだけだ。
そうやって溜めてったら、いつか崩れて、俺たちを押し潰す。
...お前の部屋が危うくなるとこだったみたいに」
唇が、やっと緩んで、でもまだ肩は震えていた。
「話してみ?」
「あ、あなたは、動物実験...反対派、ですか?」
「あー...」
そこか。
上手に着地する言葉を探していると、堰が切れた。
「僕、研究で動物実験もしてます。
今日、ちょっとそれで嫌なこともあって...凹んでて、
もしあなたが動物実験反対で、
だから僕とはやっていけないって言われたらどうしようって考え出してて、
だったら会社辞めても、貯金もまああるし特許料も入るし
この分野の翻訳も出来るから生活費は何とかなるだろうって、
...そこまで考えたら、愕然となったんです。
僕の生活、人は通り過ぎて行くだけで、
研究だけが変わらない筈だったのに。
...こんな生活能力ゼロで人としてダメな僕が、そこでだけ突出しているから、
この世に存在が許されてるようなものなのに。
あなたと一緒に居るためにあっさり放り出してしまえるなんて。
あなただっていつ、愛想つかすか判らない、
そうしたら僕には何も残らないのに。
でも今だけでも、少しでも長く居てくれるなら、って」
しがみつかれたシャツのボタンが、排水口に飛んだ。
薄く触れ合った唇が震えながら、まだ、言葉を紡ぐ。
「通りの手前の角から、窓に灯りがついてるのが見えると、
僕の心臓の辺りにも、ぽっと光が点いて、体が温かくなるんです。
ほんの一部分、触れてるだけで、頭の芯が痺れそうで...
あなたと繋がってるときの感じなんて、
初めは快感なのか脳貧血でも起こしたのか判らなかった位、強烈過ぎて、
具体的に思い出せないのに時々フラッシュバックする、
感触とか、匂いとか、そんな断片だけでも、TPOお構い無しで、
からだが、熱くなるんです。
僕はもう自分が知ってた僕じゃなくなって、
未体験ゾーン続きに、変わっていくのは、怖いのに、
もう、あなた無しじゃ、どうにもならない自分になったのが、
どうしてか、嬉し、く...」
喉がひりついて、言葉が出ない。
腕が勝手に、きつく抱き寄せ...た途端、ずるりと、濡れた体が重たく崩れた。
「ちょ、おい、大丈夫か?」
支えた頬は、こもった湯気よりも熱い。
濡れたタイルの上では抱え上げきれず、
腕を担いでリビングまで上げると、バスタオルに包んで寝かせた。
冷却材を額に貼ると、薄く目が開いた。
「ほれ、水分」
扶け起こして、アイソトニックを口に宛がう。
ごぶごぶ飲んで噎せる背中をさすっているうちに、
今度は前屈みに、船を漕ぎ出した。
腕の中でゆっくり仰向けにしても、穏やかな寝息は乱れない。
湯中り半分、過労半分といったところか。
「誰にも、言ったこと無かったんだけどさ」
艶やかな髪を、丁寧にタオルに包みながら、呟く。
「俺が居なきゃ、駄目だって、俺が必要だ、って」
タオルの端を握った手の節が、白く浮き上がる。
「誰かが言ってくれるの、待ってた...」
こみ上げてくるものを封じ込めるように、唇をつける。
肉付きの薄い頬から、青白い小さな耳、
そして尖った鎖骨の窪みにも。
「捲、簾」
目を上げると、琥珀色の眸が、こぼれそうに視ていた。
ぐうきゅうるるる。
「...この場面でこれですか、天蓬さん」
「...すいません」
戻る
続く(coming soon)
2003 Izu&Chiki All rights reserved.