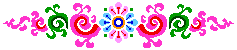
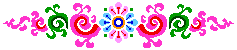
花様年華
格子越しに、彼を見つける。
ああ、ついに。
憎らしいほど、視線に敏感な男たちだから、
私は直ぐに、扇に横顔を隠す。
「さん、また逢えましたね」
翡翠いろの羽毛をゆっくり閉じて、私は、半ば閉じた瞳を向ける。
「ああ、貴方」
「今夜は買い切りで…お差支えなければ」
小女を見返って、顎をしゃくる。
「今夜は買い切りって内証に、そいっておいで。」
いくつもの雪洞を持って来て、帳台の周りに並べた小女は、
心づけの額に目を見張り、小走りに出ていった。
彼は桂花陳酒を注ぎ、黙って差し出す。
甘くきつい香りが、焼けるように、咽喉を降りて、
溜息が漏れるのが合図のように、
あの細い白い指が、私の首を引き寄せ、
薄い唇が、耳朶をなぞる。
生温い震えが、背筋から、膝の裏まで滑り落ちる。
杯が、寝台に転がり、桂花の香りが、焚いていた龍涎香を圧する。
掴もうとしても滑る緞子の上掛けの上で、
彼の重みが、胸に、腰に触れ、呼吸を奪う。
「また、殺してきたの…?それとも、これから?」
「沢山、殺してきました。そろそろ、貴女に逢えるような気がしてましたからね」
軽い口調、巧みに旗袍の裾を割る手…
腿の内側に触れる冷たさが、皮膚を泡立てる。
堅くて角ばった爪、幾らか荒れた指先の記憶は、
乳香の泡でいくら拭っても消えない。
薄絹の帳に繍いとられた、銀の花蝶が、多すぎる灯りに、羽ばたくように煌く。
(こんなに明るい中で抱かれるのは、貴方にだけ)
流されて、瞼の裏が真紅に染まる前に、
瞳を見張って、今度も、彼の瞳を覗き込む。
ひとつは偽ものだという翡翠の中に、
熱く、どろりとたゆたう、情欲を確かめるために。
他のどの男にも見たことがない、触れれば焼け爛れるような、欲望。
私に八戒という男を、灼きつけた、それ。
苦笑に紛らせて、彼は、唇を瞼に落とす。
あるべきものを確かめた私は、やっと肩の力を抜いて、
今度は唇に感覚を集めて、彼の衿をくつろげる。
私の紅に玉虫色に汚れたシャツは、前は開いても、脱がないでいてくれる。
二度目の邂逅で、私が頼んだのを、忘れていない。
「不思議な女(ひと)ですね」
彼は何故、とは訊かない。
訊いても答えないだろうことが、何故か彼には判るのだ。
大抵の女は、暗くして、と言うだろう。
こんな癖のような、柔かい笑みでは隠し切れない、
冷たいこの眼で、乱れる様をつぶさに見られては、たまらない。
素人の女がそういうのは、もう中味が空っぽの嗜みという名の格好だけれど。
(私は貴方を、つぶさに見ていたい)
汗を滴らせて、私の上で上り詰める瞬間さえ、
さん、と他人行儀に呼ぶ残酷な唇を見つめるのは、
より深く、胸を掻き毟って痛ませるとわかっていても、
もう、痛みすら悦びの隈を深くするところまで、陥ちこんでいるのだから。
どの娼婦も、全部脱いで、というだろう。
できるだけ多くの皮膚を擦り付け、熱と汗を混ざり合わせれば、
睦言も手管も大幅に節約できる。
「君が好きになったみたいだ...」
「貴方、悪い人だわ...妾(わたし)、こんなに貴方を思ってるわ」
こんな、甘ったるい安い言葉は唇をくろずませるだけ。
そして空しい言葉など、彼には要らない。
(どこか血の匂いの色を纏った貴方に、私はより深く悦ぶの)
滑らかで、骨の上にじかにぴんと張ったような彼の皮膚は、
何故か私の紅のいろを留めてくれない。
私の爪では、彼の皮膚は破れない。
いつもどこかしらにある新しい傷痕さえ、色は薄い。
(その色は人ならざる貴方と私の埋められない隙間そのもののようで、
熱しきった下肢に冷水を浴びせる悲しみが入り込んで来てしまう)
「優しくしないで。私もしないから」
「暴走したら、貴女は死んでしまいますよ」
汗に貼り付いた額髪を分けて、つける唇はやや温かい。
初めて逢ったのは、長安から砂漠を隔てた小さな宿場街だった。
妖怪の跳梁で、長安に行き来する旅人はめっきり絶え、
私のいた娼家(いえ)も干上がりかかっていた。
「、あんたは都(みやこ)に行ったらどうだい」
「姐さんは、どうするの?」
「妾(わたし)らは、長安に居られなくなって流れて来たのばっかりなんだよ。
今更戻れないやね。あんたはまだ都を知らないし、若いんだ。
イキのいい客が来たらくっついて逃げちまいな、今なら追う人手も無いよ」
まだ見たことがない都。
どこに居てもすることは同じだろうけれど、
ここで緩慢に飢えていくよりいいかもしれない。
今までも、足を抜いて行こうと囁く男も居なくはなかった。
そういう女が幸せになるなどという御伽噺は、信じたことはない。
男は危険を幾らか支払い、別の場所で女を売って儲ける。
それだけのことだ。
その夜だった。
街の外の森が紅く燃え上がり、叫び声や銃声が轟いて、
どこもかしこも扉をぴったりと閉めて息を殺していた。
彼らは炎を背に現れ、街外れの娼家をまっすぐ目指して来たという。
「開けやがれ、でねえとぶち破る!」
「ちょっと三蔵、それじゃ逆効果だって…」
彼が、寝台の下に潜っていた一番奥の主人の部屋をどうして嗅ぎ当てたかはわからない。
彼は鎧戸をかるく開けて、
「怪しいものじゃないですよ、長安から来た玄奘三蔵法師の一行です。
お風呂と食べ物と寝台とお酒、できれば女性も必要なんですけど、
提供して頂ければ、そちらの通常料金の倍額、お払いしますよ」
と、市場で果物を買うような口調でもちかけた。
「長安?!よ、よ、妖怪がうじゃうじゃしてるって森をどうやって」
「とりあえず、あそこに居たのは全部、片付けましたから。
今晩は、もう騒ぎはないでしょう」
「、お客だよ、風呂を用意しな」
いつもなら客について入って来る主人が、扉を開けるなりそそくさと逃げた。
焼け焦げた衣服、黒くこびりついた血、異臭が鼻を衝き、
煤けた顔の中で、射抜くような碧の瞳が、私を貫いた。
(この人、人間じゃない。…殺されるんだろうか)
頭ではそう思いながら、足は、ふらふらと彼の方へ向かった。
「駄目です!」
彼は、私に触れなかったのに、丸めた布団のような感触のものに、押し戻された。
「怪我を…」
「殆ど、返り血です…妖怪の血で、貴女には毒かもしれない、
まず、洗い落とさないと」
長い間湯を浴びて、湯殿に掛けてあった寛衣をひっかけた彼は、
若く、美しい男だった。
「ついさっき、僕は、何十人か、妖怪を殺して来ました。
貴女が欲しいけれど、手加減が効かないかもしれない。
怖かったら、出て行って下さっていいですよ。
お代は同じに払います」
私は、ただ、爪先立って、彼の瞳を覗き込んだ。
先刻よりよほど穏やかになったけれど、燠火のように、消えやらぬ、情欲。
月々の忌みの日に、内腿を伝う、どろりと熱い血に似て、
もっと熱く、からだの奥まで灼け爛れさせる、むき出しの、命の滴り。
ただ流されてきた切り売りの日々の中で、私は、初めて、
欲しいものをみつけた。
「僕らは、西に行くんです」
「西?」
「吠登城っていうところにね」
彼は、私の腰に腕を廻し、ぴったりと抱き寄せた。
湯上りでさえ、いくらか冷たかった皮膚が、
漸く、同じ温度に温まって、褥の中は心地良い。
「長いの、その旅?」
「生きて帰れるかもおぼつかないですね」
(私のことなんか、忘れてしまうんだ)
(続)