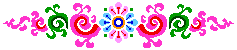
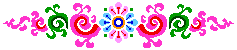
花様年華・続々
「…死ぬ、死んじゃ、う」
この言葉が、突き上げる熱の塊とは関係なく、白く、雷のように私の内部(なか)を灼く。
上り詰めた男の重みを避けて、暗い帳台に顔を伏せる。
徐々に靄が晴れる眼に映るのは違う顔、取り戻す嗅覚に訴えるのは違う匂い。
せめて敷布に焚き込めた香に埋もれて、少しでも長く、現と夢のあわいに、居たい。
だが男の手は容赦なく、私の顔をすくい上げて、見つめようとする。
首に嵌めた制御装置。人の形をした人でないいきもの。
「ほんとに死んじまうかと思ったぜ、 …だけど見かけと違ってしぶといからな、おめえは」
「…女は強いのよ」
いくら、お宝を積まれても厭だ、と妖怪を嫌がる妓ばかりだから、
妖怪の客でも取るといえば、どこの娼家でも諸手を上げて迎え入れる。
西へ、危険を承知で連れていって儲けようとする男も誰かしら、居る。
人のかたちを失った妖怪に食い殺される、と怯える女たち。
でも私は死ぬときを決めていたから、そんな目に遭うとは思いもしない。
「なあ、…おめえ、揚代はたんまり預けとくからよ、他の客とらねえでいられねえか?」
「貴方、毎日来てくれて?」
「今なら、暇だからできなくもねえが…まあ、やめとくか。
一人の男で持ちきれる女(たま)じゃねえしな」
私は唇だけで微笑う。
ただ一人の男にしか充たされなくなって、他の男にいくら抱かれても、飢えている。
でも理由など口にはしない。男が理由を欲しがるのは、望むものが手に入らないときだけだ。
「もうすぐ、三蔵一行ってのが来るんで、ちっと忙しくなる」
濡れた肩が震えても、男は、まだ寄せ返す慄きの名残だと思うらしかった。
「俺らは、そいつらを待つのが今んとこの仕事だからよ。
−お前も長安の方から流れてきたんなら、噂ぐれえ、聞いてんだろ?」
「−そうね。妖怪を殺してギラギラした目のまま女買いに来るいい男たちの噂なら」
「何ぬかしやがる」
男は床に落ちた服を探り、折りたたんだ紙を取り出した。
「へえ、美い(いい)男か?女みてぇな面のも居るじゃねえか」
男が指さす人は眼にはいらない。
冷たい碧の瞳と薄く笑った唇の彼の姿しか見えない。
じいんと、重い熱が、乳房の中から、ゆっくりと内側を灼いて、下りていく。
靄がかかっていく頭のどこかで、かちりと噛み合った歯車が、なめらかに廻り出す。
そっと肢を絡めると、男は紙を放り出して、乳房に顔を埋める。
湿った頭髪を抱えこみながら、私はうっとりと、「…死ぬ」と呟いた。
「奴らは必ず女買いに現れんのか?」
「そう聞いてるわ」
「ここらじゃ、ここ一軒じゃねえか?」
顰めた鈍いろの眼の下で動いている考えはあまりに浅はかで、
私の思惑どおりで、つい笑いそうになる。
「おめえはその日はどっか、隠れてなよ…奴ら、気狂いみたいなもんだからよ?」
私は、もっと狂ってる。でもそんなことは言うことはない。
口にしない言葉の数が多いほど、女の奥行きは深まる。
「ねえ、お酒…」
「今日はほんとに、どうしたんですか」
私は身を起こさず、彼の首に腕を絡めた。
彼の瞳を覗き込み、片方の指で唇をなぞる。
「…お願い」
唇が触れ合う感触は、ぬるくなった酒の甘さよりも、
焼け爛れるように、私の内部(なか)を、かきまわす。
「早く、」
シャツをはだけ、前をせわしくくつろげる。
足音が、確実に近づいてくる。
扉が、破れる。
彼が押しやろうとした手よりも迅く、
私は切っ先の前に身を投げ出す。
熱い。
私の名を喚いていた男が、粉々の肉片になって消える。
どんどん、見えるところが狭まって、声が出ない。
千鈞の重さがかかる唇の端を上げて、抱きとめている彼を見上げる。
シャツを染め、皮膚を汚す血は私のもの。
やっと、貴方のからだに色をつけられた。いっときだけでも。
寒い。
ああ、もう、眼が見えない。
「−今日、僕は誕生日だったんですよ」
そして闇が全てを閉ざした。
劇終
戻
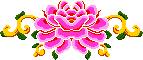
素材提供:Aaron's tools 様