

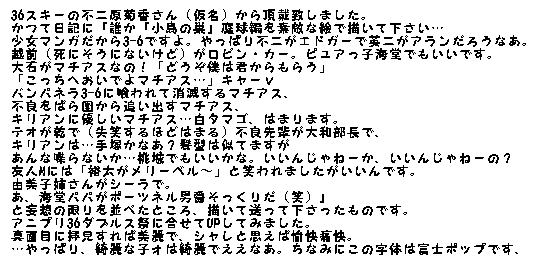
おまけ:不二原様にお礼に差し上げたお話
ペニーレイン
不二は貯水槽の日陰に座っていた。
「不二、みっけ」
「見つかっちゃった」
不二は小さく笑みを見せて、読んでいた本をパタンと閉じる。
「何読んでたの?」
ぴったり隣にくっついて座る。
開いて見せてくれた文庫本は、予想と違って漫画だった。
「『ポーの一族』?」
「姉さんに借りたんだ」
ページを傾けると、さらさらと絵がこぼれてしまいそうに見えた。
細い線が、綺麗な…男の子?や空や木々を流れるように描いている。
「あ、この子、不二に似てる」
指差した子は、不二によく似た髪のかたちをして、雨の中を走っていた。
「この子はアラン。主人公のエドガーっていう子が、
大事な妹、メリーベルを殺されて、ひとりぼっちになってしまったとき、彼を仲間に加えたんだよ。
…エドガーはバンパネラ、吸血鬼、で。
だからエドガーも、仲間にされたアランも、永遠に14歳で生きるんだ。
…ねえ、英二、永遠に14歳で居たい?」
ぼんやりと遠くを見て話していた不二が、唐突に俺の方を向いた。
茶がかった目は、俺にはわからない強い感情を浮かべている。
…それは、俺を欲しがるときのせつない色とも違っていて、
こんなに近くに居る不二に、手が届かないみたいな気がした。
思わず、目の前の不二のシャツをぎゅっと掴んだ俺を、不二は柔らかく、抱き寄せる。
不二の心臓の音が聞える、不二のシャツの匂いがする、ああ、ちゃんと、ここに居る。
「不二、不二は?」
「僕は厭だな。想像してみてよ英二、
家族も、クラスの人間も、テニス部の仲間も、皆年を取って変わっていって、
僕を残して、死んじゃうんだ。そんなの寂しすぎるでしょ」
「そうだにゃ…」
そしたら、おーいしとダブルスも出来にゃいんだな…
不二も居なくなっちゃうんだ。俺を置いて卒業して、就職して、結婚して…そんなの、厭だ。
目と喉が熱くなって、俺は不二の肩に強く額を押し付けた。
不二の指が、俺の耳を掠めて、頬から首を撫でていく。
「でも、僕は勝手なんだ。英二がずっと今のままだったら素敵だ、なんて、
ちょっと思ったりしたよ」
「え…?」
「この首が太ーくなって、手とか足もぼーぼーでごっつくなっちゃったりしないで、
ずっとずっと猫みたいで大五郎抱っこするのが似合う英二のまんまでいたらいいな、なんて」
「にゃんだよそれー!俺が寂しくってもいいのかよ不二は!」
ぶっとふくれて、腕から逃れる。
「寂しくなんかさせない」
振り返った不二の顔には笑いのかけらもなかった。
「僕がずっと、一緒にいる。僕がおじさんになってもおじいさんになっても英二が厭じゃなければ。
ううん、英二がそうなったら、僕もバンパネラになる。英二となら、僕は寂しくない」
世界が僕を置いていっても。
そう囁いて、不二はきつくきつく、俺を抱き締める。
「…俺が首、太くなっても、やっぱり傍にいる?」
「うん」
「ぼーぼーでごっつくなっても?」
「うん」
「禿げてもデブってもジジイになっても?」
「…うん」
「なんか今、間があったにゃ」
「ちょっと六角中のオジイになった英二想像してみただけだよ」
「う…」
「それでも僕はこうしてキスもするし抱き締めるし、
英二が大好きでいる、きっと、ずっと」
「俺も、だよ」
唇が今みたいに柔らかくなくなっても、
煙草とか、オッサンのにおいになっちゃっても、
変わらないものがきっとある。
欲張りで我儘で、少し意地悪な不二と、
きっと、ずっと、一緒に居る。
いつのまにか降りだした細い雨が、俺たちの髪や肩をしっとりと濡らす。
このまま動かなければ、溶け合ってしまえるような気がした。
Fin.