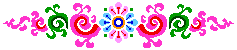
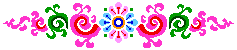
花様年華・続
二度目までは、まだ偶然を装える。
「貴女…半年前に?」
「妾たちは、どこにでも、買う人があれば流れます」
「さん、でしたね…」
微笑の底に、ことりとぶつかる、冷たく硬い光。
どちらの眸が贋物でも、本物でも、その冷たさは、
すぐに命を失う失う人間(ひと)のものとはかけ離れている。
脚の奥は、いつも濡れている。
私がこのたつきに誂え向きな理由のひとつ。
でも。
(瞳まで蕩かすのは、貴方だけ)
西へ、行きたいという願いはすぐに叶った。
「人やモノが途絶えてるから、都のモノを運んできゃあでかい儲けがあるってもんよ。
ここでちぢかまって暮らしてたっていつ妖怪どもに嬲り殺されるかわかんねぇなら、
いちかばちか賭けて、でっかい金掴もうとして死ぬ方が未練もねえやな」
無邪気に、欲に顔を光らせた男は、私の眼を覗き込んだ。
「一緒に行くか?おめえだって、ここで朽ちたくねえんだろ?」
何かを願うこと、欲しがることを知ると、
その欲望が、自分をどこかへ動かしていくことも、
どこまでもぼんやりとしていた世界にただ一つ、はっきりと見えるものを指し示すことも知った。
伸ばされた手を掴み、私は、初めて、紅い軒灯の門から出た。
明日の寝場所がわからないことも、街の人込みを歩くことも、
あんなに怖かったはずの何もかもが、触れれば崩れる燃え殻のように、
なんでもないことだったのを知った。
新しい娼家(いえ)で話が決まり、金を受け取って出ていきかけた男が、振り向いた。
「おめえは、何をめがけてる? 男…だよな、やっぱり」
私は黙って、ただ、微笑った。
「俺は担ぎきれない位のお財(たから)を持って戻って、おめえを買い切ってやるから、達者でいろよ」
白い歯を光らせて、闇のなかに、かなしい笑い顔を残し、男は去った。
商売女は、唇は許さない。
彼は約束事をよく心得ていた。
けれど髪を梳く指はひどく優しくて、
いっとき、彼の皮膚に宿ったぬくもりを少しでも長く留めたくなる私の腕は、
知らず知らず、彼の首にからみついてしまう。
「さんのこと、何度も思い出しましたよ。
柔かくて、優しくて、僕みたいな凶々しい男を喜んで受け容れてくれる。
貴女の前だと、虫も殺さないみたいな振りもしなくてよくて…やすまりますね」
震えるほど、嬉しかった。
でも、そういう気持ちに慣れていないから、いつものような微笑いしか、
私には出来ない。
「この生業は長いんですか」
「苦界(ここ)しか、知らないの。母親もこの商いで、父親は知らない」
「…すみません」
「謝ることじゃないわ。他に知らないけど、そんなに悪いところじゃない」
「でも…貴女はここでは、商品でしかない。一皮剥けば、死人が骨まで食われるような侘しいところでしょう」
「外は、そうじゃないの?」
彼は、はっと口を噤んだ。
別にやりこめる積りはなかったけれど、彼の石の心のどこかを揺らしたらしかった。
でなければ、唐突にあんなことを喋り始めたりしなかっただろう。
「僕が、一緒に暮らした女(ひと)も、同じ商売をしてました。
男たちが金を払うことの他に、自分に価値があると確かめる手段が見つけられなかった。
でも、店にとっては金を生み出すモノでしかないし、
客にとっても欲求を発散する商品でしかない。
でも人間であることを無視されることは、自己嫌悪の強い人間には一種の安定剤だったし、
そうやって沢山の自分以外の人間の下らなさを確認すると、
自分だけが醜かったり、卑しかったりしない、と安心できた。
自己嫌悪が強くて傲慢な人間が、そのまま頑なに生きる手段でもあったんです。
僕と逢って、自分と殆ど同じ人間が、ひどく自分を必要としているとわかると、
商売を止めましたけれど…」
「自分と…同じ?」
「ええ。双子の姉でしたから。生まれてすぐ別れ別れになってたんです」
なぜか、そのときの彼の瞳は他のときに見たことがないほど穏やかで、
まるで楽しいことを話しているようだった。
「自分とそっくりな人間とするなんておかしいですよね。
でも僕たちは初めて、哀れまれたり、蔑まれたりする心配抜きで触れ合える相手を見つけたんです」
多分、私に揺らされた分、私も揺すぶって、突き放そうとしたんだろうけれど、
私の居る世界では、珍しいことでもない。
父親に、兄に、こじ開けられて売られてくる娘、息子を客にとってしまう女。
私にとっては、姉だろうが、笑いながら話す彼の内に、そんなにも食い入っている女(ひと)が居ることに、
胸が痛んだ。
「そのひとは…?」
「死にました。僕の前で、胸を突いて」
彼は、喋りすぎたことを悔いるように、性急に私の脚の間に割り込んできた。
(続)
戻
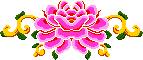
素材提供:Aaron's tools 様
![]()